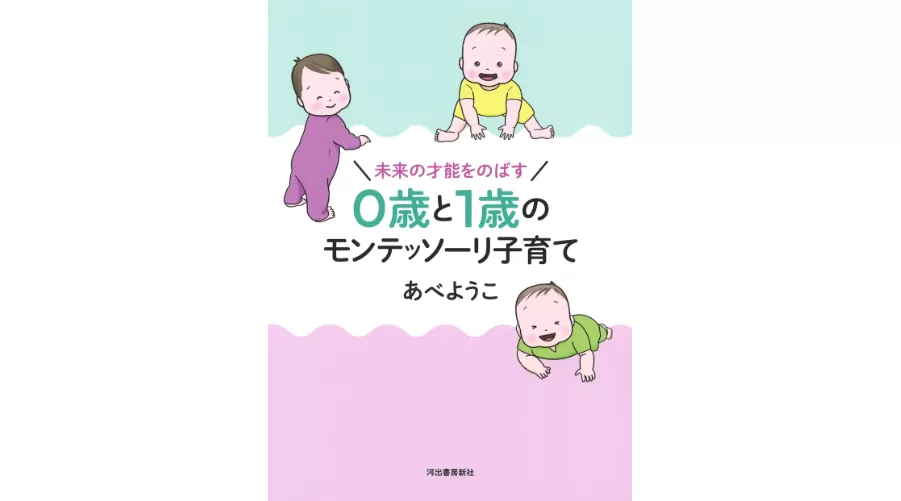
著者
著者:あべようこ
モンテッソーリ教師/教育コンサルタント/保育士。上智大学文学部教育学科卒。国際モンテッソーリ協会(AMI)公認(0‐3歳)国際教師資格取得(アメリカ・サンディエゴ及び大阪コース)、日本モンテッソーリ協会公認(3‐6歳)国際教師資格取得(東京コース)。モンテッソーリ教育のポータルサイト「イデー・モンテッソーリ」を運営し、国内外のモンテッソーリ教育を広めるため、インターネット上でもモンテッソーリ教育をわかりやすく解説したマンガを発表するなどの活動を行っている
本記事では、こんなことが分かります!
話題のモンテッソーリ教育について学べる
子どもが成長するための親から子どもへの接し方と環境作り

子どもが生まれたけど、どうやって子育てしたらいいんだろうか?
子育ての経験もないし、誰かに教えてもらえるわけでもないし・・・



そんなときは、「未来の才能を伸ばす 0歳と1歳のモンテッソーリ子育て」を読むことをおすすめするよ!
【結論】子どもの才能を伸ばすために、子どもの「してみたい!」を叶えられる環境作りを!
モンテッソーリ教育とは?
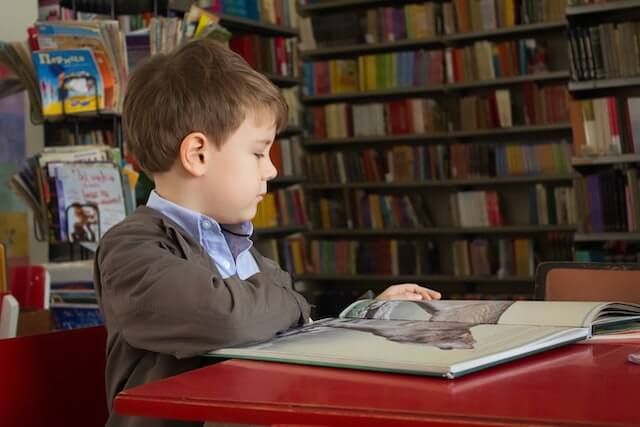
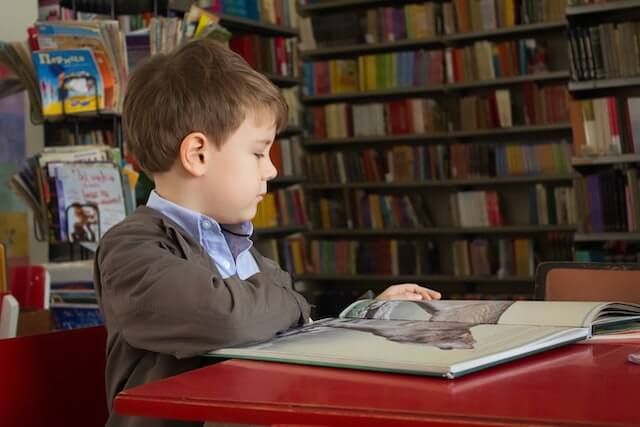
イタリア人の女性医師のマリア・モンテッソーリが開発した教育法で、欧米を中心に世界中で実践されています。最近では、将棋の藤井聡太さんが受けていたことでも話題になり、「子どもの才能を伸ばす教育法」などと言われ、日本でも人気が高まっています。
日本では2歳から6歳ぐらいまでの幼児向けの教育法として知られていますが、実は欧米では乳幼児から高校生までの教育法が確立されています。
中でも著者が重要だと考えていることが、0歳から1歳の赤ちゃんへのモンテッソーリ教育です。
脳も体も脅威的に発達する時期。
この時期の赤ちゃんの課題は、「自分とまわりを信じる心を育てること。」です。
モンテッソーリ教育は、個人の自発性や自己学習を重視することで知られています。
モンテッソーリ教育は、子どもの発達段階に合わせた教材や環境を提供することで、子どもたちが自ら学び、成長することを促進します。具体的には、教材や環境が子どもたちの好奇心や探究心を刺激し、自発的に取り組めるような設計になっています。
また、モンテッソーリ教育では、子どもたちが自分自身や周りの人や物に対する関心や興味を持つことを重視します。そのため、教師は子どもたちが自己決定力を持って、自分自身を発見し、育てることができるように、子どもたちを見守る役割を担います。
モンテッソーリ教育は、世界中で広く実践されており、幼児教育や小学校教育などの段階で採用されています。この教育方法は、子どもたちの能力を最大限に引き出し、自己決定力や自己調整能力、協調性などを育むことができるとされています。
第1章 赤ちゃんが生まれる前に-妊娠中の過ごし方-


ママの声で、心のよりどころをつくる。
お腹の赤ちゃんにたくさん話しかけてください。
実はこれが、生まれてきた赤ちゃんの「安心感」へとつながります。
音の記憶が、お母さんの胎内から外の世界へ抜け出した赤ちゃんが、新しい世界に慣れていくための助けとなります。
「寝る」「授乳」「運動」「おむつ替え着替え」コーナーを作る。
①「この世界はいいところだな」
②「自分は何でもできる有能な存在なんだ」と気持ちを育てること。
この2つは、モンテッソーリ教育では「心理的な二本の足」と呼ばれています。
「まわりを信頼する気持ち」が育つと、チャレンジを楽しめる子になります。
「自分を信頼する気持ち」が育つと困難にぶつかってもめげずに前進を続けられる子に成長します。
第2章 赤ちゃんが生まれたら-産後の生活の始め方-


赤ちゃんとママができるだけ密着して過ごすことが大切です。
妊娠中は赤ちゃんとママはずっと一体でした。しかし、出産後、2人は突然別々の存在になります。お互いショックを受けてしまうため、2ヶ月間は「できるだけ密着して過ごすこと」。この期間で新しい関係性を受け入れるための、スモールステップとなります。
またこのスキンシップが新生児の脳の発達したを助けます。
授乳は、赤ちゃんを観察し、赤ちゃんのリードに合わせて飲みたがるときにあげましょう。
赤ちゃんにまつわるママの悩みの代表的なもののひとつが「寝かしつけ」でしょう。
赤ちゃんが夜、なかなか寝てくれず、睡眠不足で困っている人は少なくないと思います。
①夜寝る前には、部屋を暗く静かに
②夜中に起きても明るい電気をつけずに、しばらく様子を見る
③朝は決まった時間にカーテンを開けて、日の光を入れる
④日中はできるだけ、午前中に太陽の光をあび、身体を動かす
⑤夜の入眠儀式をつくる
例えば、決まった時間に部屋を暗くして、ママやパパがお歌を聞かせる
⑥寝る場所に刺激になるものを置かない
第3章 赤ちゃんの成長をサポートするポイント-0ヶ月〜5ヶ月ごろまで-


「子どもには生まれつき、自分で自分を教育できる力が備わっている」、いわば「子育ち力」とも言える、赤ちゃんの素晴らしい能力があります。
①吸収する心
②敏感期
③人間の傾聴性
吸収する心
赤ちゃんが生まれてくるときはみな、真っ白な心で生まれてきます。
環境に適応できるように、人間の赤ちゃんは特別な働きをする脳をもっています。
この時期に吸収したことは深く脳に刻み込まれ、一生を通じてその人のベースとなります。順応性が高い時期だからこそ大人は「環境づくり」に気を配る必要があります。
敏感期
敏感期の子どもは、興味をもったことへの感受性が高まり、集中して同じ動作を繰り返します。自分で成長しようとする子どもの邪魔をせずに見守りましょう。
人間の傾向性
人間ならではの普遍的な知的好奇心のこと。「これをせずにはいられない!」というもの。
例えば、
・周囲にあるものを知るために探索したい。
・自分がどこにいるか知りたい
・コミュニケーションしたい!などです。
ここで、子育てのヒント!
ことを意識しましょう。
第4章 おすわりやひとり歩きができるようになったら-6ヶ月〜2歳ごろまで-


たくさん動く時期のお部屋づくり
「運動敏感期」には、好きなだけ動けるように
生後6ヶ月を過ぎると、赤ちゃんは、ますます活発に動くようになっていきます。
成長に合わせて、赤ちゃんが積極的に動けるようにサポートすることで、さらに赤ちゃんの自信を育てることができます。
さまざまな動きを身につけたいこの時期には、ハイハイ、ずりばい、つかまり立ちや伝い歩きが、充分にできるスペースを、確保してあげられるとベストです。
「いたずら」じゃなく、「お仕事」
おすわりができるようになるころからは、赤ちゃんの「いたずら」が目につきはじめます。
ついつい、「何やってるの!」「いたずらしないの!」と声をあらげてしまいがちですが、モンテッソーリ教育ではこうした行動はいたずらではありません。
名前を覚える
モンテッソーリ教育では、子どもにものの名前を覚えてもらうために、「セガンの三段階レッスン」を説明をおすすめしています。
フランス人エドワード・セガンが考案したことばのレッスン法です。
※間違いを直接指摘するのはNGです。
(3については、3歳ごろまではしなくてよい。理由は、わかっているけど発音ができない、言いたくないことも多い時期のため。)
とても簡単に実践ができます。
絵本の選び方
身近なものが描かれている(服、野菜、果物など)
絵なら現実に近いもの。
ページが厚手のもの。
低めの位置に本棚を置く。(ハイハイでも取りやすい。)
第5章 これから起こることで知っておきたいこと-2歳〜3歳ごろまで-


最後に、モンテッソーリ教育で育った子はこんなふうになります。


自分を信じているので自信を持って何でも挑戦します。
まわりと人を信じているので安心感をもって過ごせます。
そして自信と安心感をたずさえて人生の中で何度もおとずれる困難を乗りこえる力を持った人になるでしょう。
ルールを伝えつつ、見守りましょう。
モンテッソーリ教育は、「何でも好きなことをさせて注意しない教育法」と誤解を受けることがありますが、そうではありません。
小さなときから最低限のルール(自分も、まわりも、傷つけないこと)はしっかり伝えていきましょう。
まとめ
本書を読み、子どもに本来備わっている「自分で自分を教育する力」や「○○をしてみたい!」などの欲求を知ることで、親がどこまで手助けするかを判断する上で、役立つ情報が沢山ありました。まずは、赤ちゃんが何を考えているか観察して、環境を整え、成長を見守る(過保護になりすぎない)ことで、赤ちゃんの成長に繋がっていくと思いました。イラストが描かれていることもあり、とても分かり易く、理解しやすい内容でした。現在、妊娠中の方や子育てを始めた方におすすめの本です。
【著作権者(著者、訳者、出版社)のみなさま】 当ブログでは書籍で得た知識を元に制作しております。あくまでも、書籍の内容解説をするにとどめ、原著作物の表現に対する複製・翻案とはならないよう構成し、まず何より著者の方々、出版・報道に携わる方々への感謝と敬意を込めた運営を心懸けております。 しかしながら、もし行き届かない点があり、記事、動画の削除などご希望される著作権者の方は、迅速に対応させていただきますので、お手数お掛けしまして恐れ入りますが、問い合わせフォームからご連絡をよろしくお願い致します。







