著者について
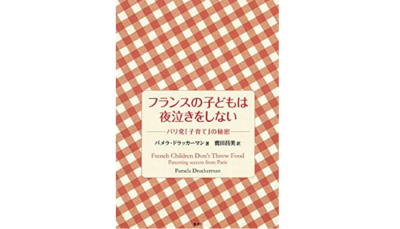
筆者:パメラ・ドラッカーマンさん
アメリカ人女性、夫イギリス人、パリ在住。

子育ては大変だな・・・夜、子どもを寝かしつけてもすぐに起きてきしまうし、もう毎日クタクタよ。



そんなときは、「フランスの子どもは夜泣きをしない パリ発「子育ての秘密」」を読むことをおすすめするよ!
今回、この記事を書くにあたり、現在、子育て中の中央大学卒の友人に監修をしてもらいました!
本記事では、こんなことが分かります!
フランスの子育てでは、親が子どもの自立と制御を促す!
親も楽しめる人生でありたい!ルールを設けて子育てをもっと気楽に。
【結論】フランス流の子育ては、「自分の人生」と「子どもの人生」を大切にする。
第1章 パリ移住と妊娠


英米人の女性は大抵、妊娠して母になるには宿題がついてまわり、本から勉強する。そして、躍起になって疲れる。
フランス人はそこまで気にし過ぎないで気楽に構える。
第2章 パリの妊婦はなぜスリムなのか


フランス人女性は妊娠していても楽しみを捨てないことを誇示している。女らしさを忘れてはいけない、と考えている。妊娠中だけに食べるのを我慢しているのではなく、普段から過食することがない。
パリでは87%が無痛分娩が当たり前のこと。
第3章 フランス人の赤ちゃんは朝までぐっすり眠る


米英人は、赤ちゃんが親の睡眠時間を奪うのは仕方ないことと考える。
フランス人の赤ちゃんは生後3-6ヶ月の間に朝まで8時間眠れるようになり、親は夜邪魔されずにまとめて眠れるようになる。
赤ちゃんが、まとめて眠ることを自力で学ぶという。
赤ちゃんが生まれたら、夜にすぐにあやすのはやめる。赤ちゃんが自力で落ち着くチャンスを与える。観察してちょっと待つ。
赤ちゃんには2時間程度の睡眠サイクルがあり、谷間に目を覚ます。そのサイクルをつなげる学習をしているうちに泣くのは当たり前だが、その学習を妨げないようにする。
自転車に乗る練習に似ている。完全に目を覚ましたら、抱き上げてあやす。泣かせっぱなしにしろと言うのではなく、赤ちゃんに学習するチャンスを与えるということ。
夜、お風呂に入れ歌を聞かせミルクを与え、赤ちゃんをご機嫌にさせる。まだ目を覚ましているうちに、ベッドに寝かせる。
夜中にミルクを飲ませなくて良いのかと言う疑問には、胃を休めるのは体に良いとする。多少のフラストレーションでは赤ちゃんは潰れない。
第4章 お菓子作りは教育の宝庫


睡眠同様、フランスの赤ちゃんは食事も4時間待つことができる。なぜなら、赤ちゃんは常に学習をしているから。
幼少期に待つことを覚えると、ティーンエイジャーになってからもストレスに取り乱さない傾向がある。
フランス人は子どもを服従させるためではなく、自らを制御できる方があらゆることを楽しめると考えている。
待つことが上手な子は、自分で考えて気を紛らわせるとこができる子。気を紛らせる方法を知らない子は、待てずにおやつを摘んでしまう。
意志の強さを決めるのは禁欲的かどうかではなく、フラストレーションと感じずに待つテクニックを知っているかどうかが大切。
子どもが自分はなんでも欲しい時に手に入れることができる、と思わせないようにする。
その1、生後2ヶ月、赤ちゃんはだいたい毎日同じ時間に食事をさせる。
その2、赤ちゃんの食事は少量をちょこちょこでなく、一回の量を多くして回数を少なくする。
その3、赤ちゃんは家族のリズムに合わせるべき。
フランス人ママは母乳にこだわらない。
産後体型維持、平日パンを食べない。土日と平日夜の外食はなんでも好きなものを食べる。
働いていないママも、週に数時間保育施設に預けてヨガ教室や美容室に通う。自分を大切にする。
フランスの魔法の言葉


挨拶を大切にする。こんにちは、ありがとう。心がこもってなくても。あなたを人間として認識していますよ、という合図になる。
とくにこんにちは、が大切。子どもが挨拶をすることで存在を認められる。フランス政府発行の小冊子にも、礼儀正しさのための挨拶が書かれている。
わがままな子にならないため。与えてもらうだけでなく、与える立場でもあることに気づかせる。子どもと大人を対等にさせる。
フランス流、夫婦円満の秘訣


子どもが巣立ったあと、夫婦で良い関係性を維持する。
「大人の時間」は基本的な人間の欲求。1人でいられる世界が必要。
フランスの2週間の休暇は、ふたりの絆を強くし、子どものためにもなる。
カップルの時間、例、週末の朝は子どもに親の寝室に入らせない決まりをする。
フランス女性は男性に自分と対等であることを期待しない。男性の欠点やミスについてくどくど言わない。女性の方が出来が良く上等だと笑う。だから男性はやる気を無くさない。
フランス流の食育は驚きの連続


5.6歳の肥満率、フランス3.1%、
4.5歳、イギリス10%。
離乳食を、米粉からでなく、野菜から始める。それぞれの野菜の味を事細かに説明し、一生のお付き合いの始まりのように話す。
食育は子どもを味覚という豊かな世界へ誘う手段と考えている。フランス政府ハンドブック、新しい食材を発見して喜ぶ赤ちゃんが描かれている。
大切なのは、子どもを安心させ、新しい食材について教えてあげること。
「何を食べたい?」でなく「今日の食事はこれ」という。食べきれなくても良い。家族全員が同じものを食べるのが大切。大人と同じように扱う。
お菓子は生活の一部なので、がっつくことはない。
なにかがちがう、フランス人の親の叱りかた


子どもは言うことを聞かないのを仕方がないこと、と考えず、親は確信を持って本気でノーを言って聞かせる。
親が上、子が下のヒエラルキー、枠組みを形成する。「〜する権利はない」「その代わり、別の〜する権利はある」子どもに話聞かせるときは目と目を合わせて真剣な口調で言う。
目を大きく見開いて言う。声を荒げるのではない。なぜ禁止なのか理由を必ず説明する。
基本的には、禁止よりも許可を与える機会を多くする。子どもが何かを欲しがったり触りたがったりする前に、親に許可を求めるようにする。
寝かしつけの時間でも、厳しさと大目に見るバランスが大事。
例:部屋を出ては行けない。しかし部屋の中では自由に過ごして良い。
すると遊んだり本を読んだあと自分でベッドに入る。
フランス思想家ジャン=ジャック・ルソーの考え方。「与えるときは喜んで与え、拒否するときは渋々拒否すること。しかしいったん拒否したことは取り消し不可能だ。
いくら懇願されても方針を変えてはならない。ノーを言う時は、キッパリと。
子どもには子どもの人生がある
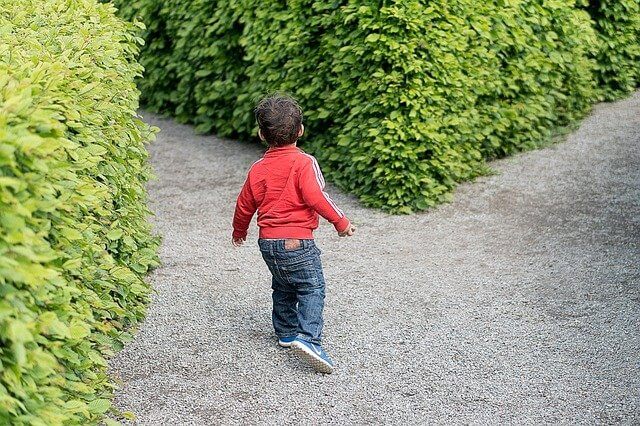
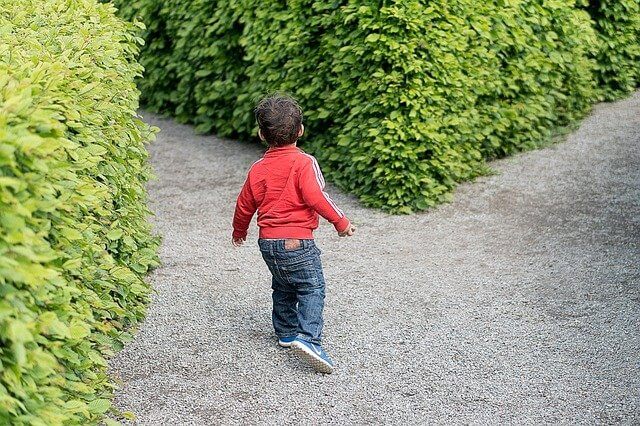
子どもを過度に褒め過ぎない。
頻繁に褒められると、肯定的な評価に依存するようになる。褒められないと不安になる。賞賛を浴びすぎると、リスクを回避し自主性を欠くようになる。
まとめ
本書を読んだ感想は、フランスの子育てと日本の子育ての間には、自主性あるいは制限やルールがはっきりしていることが大きな違いだと思いました。最近では「子どもは褒めて伸ばせ!」と言われがちですが、しっかりと自主性や自分への制限の訓練ができてこそだと感じました。また、生まれてから「子どもは子どもの人生」としっかり親が捉えて子育てすることで、大人と対等に子どもと接することができると思いました。子育てで悩んでる人は多いと思います。どんどんこのような無料の情報を活用していきましょう。






